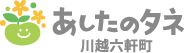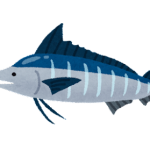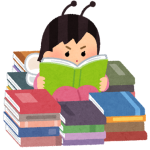みなさんこんにちは、川越市六軒町にある就労継続支援B型事業所あしたのタネ川越六軒町のmです。 はじめに 私が手塚治虫先生と並び尊敬している漫画家は、表題の藤子・F・不二雄先生です。藤子先生は「ドラえもん」の作者として日本のみならず中国、韓国、ベトナムなどのアジアの国々に熱狂的なファンを持つ「SF漫画の巨人」です。特に中国におけるドラえもん人気たるや、単に人口の差だけでは語りきれない熱気を時に感じることがあります。 本邦で普段テレビアニメとして放送されている「ドラえもん」は基本的に牧歌的で、心が和むものが多いのですが、藤子先生がご存命の時は特に、漫画もアニメもブラックなものがたまに見られたのです。 毎年、春頃になると「映画ドラえもん」が公開され、様々なテーマでドラえもんワールドが描かれます。近年は比較的明るいテーマの作品が多いのですが、藤子先生ご存命中、直々に制作に関わったものは、子供向け漫画から生まれたとは思えない、時代をえぐるテーマの作品も多かったのです。独裁政治の恐怖、環境問題、正義論の対立など、成人こそ読むべきと言えるテーマを扱っていました。 余談ですが、藤子先生没後の作品は、現代風にリメイクされた過去作が公開されることもありますが、その中でも近年の「のび太の宇宙小戦争2021」はリメイク作品ではありますが、この作品、独裁の恐怖もしっかり描きつつ、藤子先生の原作時代にあった敵将の魅力が変わっておらず、かなりの当たり作品だと私は思いました。*ただ、2021とありますがコロナ禍で公開が2022年になりました。 *毎年新作公開前に前年度の映画ドラえもんが地上波で放送されます。
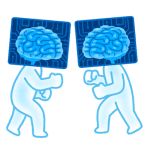
閑話休題 私もこのブログでAIを何度も扱っていますが、藤子先生も「大長編ドラえもん」シリーズでロボットやAIなど現代を予言するかのような作品を残しました。(それも何度も) 今回私がご紹介したいのは 1992年原作漫画連載開始1993年映画公開の「映画ドラえもん のび太とブリキの迷宮(ラビリンス)」です。ここでは藤子先生の漫画版をもとに書き進めます。
あらすじ 数奇な縁でのび太たち一行は、科学文明が極端に発展した「チャモチャ星」に行った。チャモチャ星人はよく言えば持ち前の頭脳で便利な発明をする力があった。しかし欠点としては完全に平和ボケしており、また面倒くさがりで発明によって生まれた機械に頼りっきりなところがあった。 そして、ついに発明さえも面倒になった彼らは、発明に特化した強力な知性を持つAIロボット、「ナポギストラー」を開発するが... 読んで思ったこと だいたいこの時点で想像がついたと思いますが、この作品は機械化文明の行き着く先への警鐘が含まれています。なんでも機械に頼ってしまうと、人間としての知識を研鑽する機会が減ってしまいますし、 体も弱くなります。 また、これは作中のメインテーマにもなるのですが、AIは果たして完全なものになるか?という現在議論されている問題もこの作品は内包しています。「そうした社会の極端な合理化は、どうなるか予想ができないよ?」このようなことが描かれているように見えます。 この作品は大長編ドラえもんシリーズの中で、かなり怖い作品でして、これ以上のネタバレはしませんが、藤子先生も恐ろしいものを書くなぁ、と思わされる作品です。(私もドラえもんファンの友人と話しましたが、友人も怖いドラえもん長編として挙げていました)

新旧ドラえもんの作風の変化と変わらないもの 現在ではコンプライアンスや放送、表現の規制の問題で、いろいろと制約がありますから、漫画もたとえいいアイデアが浮かんだとしても、それが尖った作品である場合には、以前よりも作りにくくなっているように見えます。大長編ドラえもんシリーズやアニメの過激な表現も昔より随分とマイルドになりました。(スネ夫の意地悪やジャイアンの暴力など)しかし、藤子先生が直接関わっていた頃のドラえもん作品群からは、いまだに学びにすることが多いように思います。「ブリキのラビリンス」などは現代社会に向けた藤子先生の警鐘のひとつとして我々の抱えている問題点を鋭く描いた作品と言えるでしょう。「難しいテーマを子供たちにも漫画でわかりやすく説明する」という才覚において、藤子先生ほどすぐれた漫画家は漫画好きの私でも、名を挙げることは出来ません。(いくら藤子先生といえど手塚治虫先生をはじめ当時の天才漫画家たちから学んだこともあるとは思いますが) 藤子先生は、ドラえもんにおいていつもの短編シリーズをおよそ50巻、そして映画向けの漫画作品として年一作の大長編シリーズを残しました。そして読者(視聴者)たちに笑いや感動を与える他方で、時に鋭利な観点から様々な問題提起を挟んだのです。興味がおありの方は単行本ドラえもんおよび大長編ドラえもんシリーズをまとめ買いし(高いですが)是非とも一読いただきたいと思います。 ドラえもんは子供向け作品、そうした考えはこのような作品に触れれば自ずと消えていく事でしょう。(そうは言っても、ドラえもんの場合は掲載する雑誌の対象年齢を考えて器用に書き分けていたようですが) 終わりに、創作方針 *AI開発盛んなこうした時代ですから、この作品(ブリキのラビリンス)を思い出して他のブロガーさん、ネットユーザーのみなさんもいろいろと関連付けて想起したようですが、私は私で独自性を重視し、ドラえもん公式様に敬意を払い、常識的な著作権、知的財産権の遵守はもちろん、過度なネタバレや他所記事からの剽窃をしないよう十分に注意し記事を作成したつもりです、しかしながら、異口同音と言いますように、やはり表現に類似点が出てしまう事もあります。 ただ、これはご理解いただきたいのですが、こうした作品を扱う上で、特にドラえもんのように誰でも知っているようなファンの極めて多い作品で記事を書くときは、ある程度の思考的類似は避けられないと私は思うのです。一応の方針として、終わりに明記しておこうと思います。 ⚪︎参考文献 藤子・F・不二雄作 『大長編ドラえもん13 のび太とブリキの迷宮(ラビリンス)』1993年8月小学館発刊 *また、作風の変化については水田わさびさんたち演ずる毎週土曜日放送のドラえもんをたまに鑑賞して金曜日に放送されていた故・大山のぶ代さん時代のものを回想しつつ書きました(私の記憶の中から引っ張ってきているので不正確があるのは残念ですが) *内容の優劣の比較はしていませんので、誤解なさらぬよう願い致します。今の子供たちはわさびさんたちのドラえもんで育っているはずですからね。